更新日:2025年08月04日
ED(勃起障害)の原因は多岐にわたり、ストレスや加齢、病気、薬剤などが影響を及ぼすことが知られています。EDとは、十分な勃起が得られない、または維持できない状態であり、性欲があるにもかかわらず勃起しないなどの症状が特徴です。
本記事では、EDの原因を心因性・器質性・薬剤性・混合型の4タイプに分類し、それぞれの特徴や対策、予防法を解説します。
EDは「Erectile Dysfunction」の略称で、日本語では勃起不全や勃起障害と訳されます。性交時に勃起しない、または勃起を維持できない状態を指します。
EDは、男性であれば起こりうる病気です。「性欲はあるが勃起しない」「勃起しても十分な硬さがない」「勃起が持続しない」「たまに勃起しないことがある」などが主な症状です。
EDが発生する原因は多岐にわたります。勃起は神経、血管、そして心理的要因が重なって起こる現象です。性的興奮が神経を通じてペニスに伝わると、陰茎海綿体の動脈が拡がり、十分な血液が流れ込むことにより勃起します。
これらのどれかに問題が生じると、陰茎海綿体に十分な血液が流れず、勃起に障害を起こすのがEDです。
EDは単なる身体的な問題に留まらず、心理的な要因も関係するため、どれか一つに問題があるだけでもEDのリスクがあります。
勃起障害(ED)は、多くの男性にとってデリケートな問題であり、その原因は多岐にわたります。ここでは、主な原因を以下の4つのタイプに分けて解説します。
それぞれの原因や症状に応じた適切な治療が大切です。自分に合った対処法を見つけるために、まずはEDのタイプごとの特徴を理解し、正しい知識を身につけましょう。
心因性EDは、心理的・精神的な原因により発症します。身体機能に問題がなくても起こり得るため、注意が必要です。心因性EDには、大きく分けて「一般型」と「状況型」の2つのタイプがあります。
一般型は、状況に関係なく常に発症するEDを指します。一般型には「無反応型」と「抑制型」があり、性的興奮の欠如やパートナーとの関係が原因です。
状況型は、EDの症状の有無が性行為の状況に左右されるタイプです。「パートナー関連型」「行動関連型」「精神的苦痛や適応への関連型」の3つに分類されます。特定の相手との関係や過去の失敗経験、日常のストレスなどが原因です。
| 心因性EDのタイプ | 説明 | |
|---|---|---|
| 一般型の心因性ED(状況にかかわらず常に症状が現れる) | 無反応型 | 性的な刺激に対して興奮を感じず、勃起にいたらない状態 |
| 抑制型 | パートナーとの関係性により、性的な行為自体を避けるようになる状態 | |
| 状況型の心因性ED(状況によって症状が現れる) | パートナー関連型 | 性的パートナーによって症状の有無が変化する |
| 行動関連型 | 過去の性機能障害や失敗経験からの不安が原因で発症する | |
| 精神的苦痛や適応への関連型 | 日常のストレスや気分の落ち込みが引き金となって発症する |
心因性EDは20〜30代の男性に多く見られ、性行為での失敗体験がトラウマになるケースも珍しくありません。負のループに陥りやすいため、早めの対処が重要です。
器質性EDは、主に血管系と神経系の身体的問題により発症し、40代以降に多いとされています。器質性EDの主な原因は、糖尿病・脂質異常症・動脈硬化・神経障害などです。
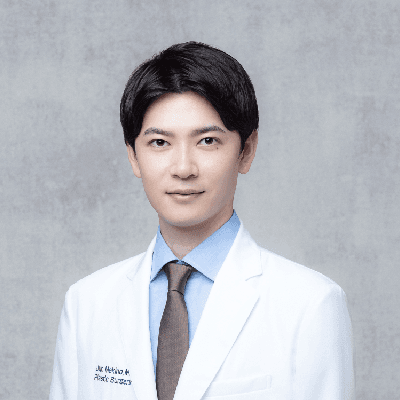
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
糖尿病性による末梢神経障害により、性的興奮が陰茎に伝達されにくくなり、EDを引き起こします。また、糖尿病は血管系と神経系の両方に影響を与えるため注意が必要です。
動脈硬化は、血管が硬くなり十分に拡張できなくなる状態を指します。陰茎動脈が影響を受けると、勃起に必要な血液量が確保できず、EDにつながりかねません。動脈硬化は大血管だけでなく、陰茎海綿体内の細い血管でも起こるため、EDが初期症状として現れることがあります。
糖尿病や動脈硬化以外にも、動脈硬化の原因となる高血圧や高脂血症といった血液循環に関連する生活習慣病を有する場合は、EDになるリスクが高いといえるでしょう。
神経障害の原因としては、脊椎損傷・脳卒中・脳腫瘍・椎間板ヘルニア・パーキンソン病などが挙げられます。神経系の問題によるEDの場合、通常のED治療薬が効きにくいため、ICI療法(男性器への直接注射)などの治療法を検討することもあります。
薬剤性EDは、服用中の薬の副作用によって引き起こされるEDです。主に以下の薬剤が原因となる可能性があります。
これらの薬以外にも、アレルギーの薬などがEDの原因となることもあります。
服用中の薬がある場合、EDを気にして自己判断で薬を中止・変更することは大変危険です。薬の服用に関しては、必ずかかりつけの医師に相談しましょう。
混合性EDは、器質性EDや心因性ED、薬剤性EDの要因が複雑にからみ合って発症するタイプです。単一の原因ではなく、複数の要因が重なり合ってEDの症状を引き起こします。
たとえば、薬剤性と心因性の組み合わせによるEDです。ある薬の副作用で中折れを経験し、それがトラウマとなって性行為の度に不安が募り、性的興奮にいたらないケースが挙げられます。
そのほか、軽度の器質性EDを抱える人が、パートナーからの否定的な反応をきっかけに心因性EDを併発することもあります。
EDの改善には、生活習慣の改善やストレス軽減、ED治療薬の服用など、さまざまなアプローチ方法があります。これらの対策を組み合わせることで、EDの症状改善を図れるでしょう。
EDの予防や改善には、日々の生活習慣の見直しが重要です。とくに運動不足・肥満・喫煙への対策をとることで、EDの予防・改善を図れると考えられます。
まず、適度な運動を心がけましょう。運動は血流を改善し、動脈硬化の予防にもつながります。
また、食生活の見直しも大切です。塩分や脂質の過剰摂取を控え、ゆっくりよく噛んで食べることによって肥満を予防できます。肥満対策により、インスリンの分泌が正常化し、血流が改善されるでしょう。
禁煙も重要な対策の一つです。喫煙は血管を傷つけ、動脈硬化を促進するため、EDのリスクを高めます。
これらの生活習慣の改善は、特に器質性EDの方に効果的です。内臓脂肪の減少はインスリンの働きを改善し、血糖値の安定につながります。結果として、血流が良くなり、EDの症状改善が期待できます。
心因性EDの主な原因であるストレスを軽減することは、重要な対策です。リラックスした精神状態を保つことで、不安や緊張が緩和され、EDの改善につながる可能性があります。
瞑想やヨガ、軽い運動など、自分に合ったストレス解消方法を取り入れるとよいでしょう。また、EDに関する正しい知識を持つことも大切であり、医師に相談しながら不安や焦りを解消することが望まれます。症状を放置すると悪循環に陥る可能性があるため、早期の対応が大切です。
ED治療薬の服用は、勃起をサポートする有効な方法です。「勃起はするが、維持が難しい」「硬さが不十分」といった場合、治療薬が効果を発揮します。ED治療薬は一時的に血流を促進し、勃起を助けるものです。
治療薬の服用を続けることで、海綿体への血液流入が増加し、EDの症状改善が期待できます。ただし、ED治療薬には併用禁忌薬や併用注意薬があるため、持病がある方は必ず医師に申告しましょう。以下に代表的なED治療薬の特徴をまとめました。
| ED治療薬 | バイアグラ | シアリス | レビトラジェネリック |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 効果や持続時間は標準的 | 効果の持続時間が長い | 即効性があり、効果が強い |
| 効果の強さ | 強い | マイルド | とても強い |
| 食事の影響 | 食後に服用すると効果が減弱するので、空腹時もしくは食事から2時間程度空けて服用する | 食事の影響は受けにくい | バイアグラほど食事の影響は受けないが、空腹時もしくは食事から2時間程度空けて服用するのが望ましい |
| 副作用 | ・ほてり ・頭痛 ・鼻詰まり など | ・出にくい | ・ほてり ・頭痛 ・鼻詰まり など |
ED治療薬は、直接クリニックに行くだけでなく、オンライン診療でも処方を受けることができます。オンライン診療を利用すれば、自宅で診察を受けられるため、忙しい人やプライバシーを重視する人におすすめです。
診察予約や診察、処方薬の支払いがインターネット上で完結し、薬は基本的に自宅に届くため、時間を有効に使えます。
ED(勃起障害)は多様な原因から発生し、個々のライフスタイルや健康状態、精神的要因などが関係します。原因を知り、適切な対策を講じることで、EDの予防・改善を図れます。
EDの予防・改善には、生活習慣の見直しやストレス解消、ED治療薬の服用が有効です。EDの原因がわからないときやEDの症状に悩んでいるときは、医師に相談してみましょう。
レバクリでは、EDのオンライン診療を行っています。場所や時間にとらわれずにビデオチャットや電話で診察が受けられ、処方された薬は自宅など好きな場所に届きます。診察料は無料なので、ぜひご予約ください。