更新日:2025年08月04日
EDの治し方について知りたい方もいるでしょう。EDは神経障害や血管障害、心理的要因などによって引き起こされ、原因に合わせて適切な対処をとることで改善を図れます。
本記事では、EDの症状や原因、効果的な治療法について解説します。自分に合った治し方を見つけるためのヒントとしてぜひ参考にしてください。
ED(勃起不全)の症状は人それぞれ異なりますが、主な症状としては以下のとおりです。
これらの症状により性機能に自信を失い、性生活に消極的になる方も少なくありません。
EDの自己診断方法として、セルフチェックテストがあります。「IIEF(国際勃起機能スコア)」や「SHIM」などがあり、Web上では各クリニックのWebサイトに掲載されています。
ただし、これらの結果はあくまで参考程度であり、正確な診断には医療機関での受診が必要です。なお、セルフチェックの結果を診察時に持参すると、医師への相談時に役立つと考えられます。EDの症状に心当たりがある場合、まずはセルフチェックを試してみるのもよいでしょう。
ED(勃起不全)の原因は、心理的な問題や身体的な問題、薬の影響など多岐にわたります。EDの適切な治療には、その根本的な原因を検討し、個々の状況に応じたアプローチが必要となります。以下で、それぞれについて見ていきましょう。
心の問題が原因のED(心因性ED)は、主に20〜40代の若い世代に多く見られます。主な原因は、日常生活におけるストレスや不安、過去のトラウマ、うつ病などです。
心因性EDの特徴として、マスターベーションや朝立ちはするものの、性行為の際に勃起が困難になることがあげられます。
心因性EDを改善するには、不安や緊張を取り除き、リラックスした状態を作ることが重要です。また、EDに関する知識不足は不安の一因となるおそれがあるため、EDの正しい知識を身につけましょう。パートナーと悩みを共有し、ともに改善を図ることも効果的な方法の一つです。
幼少期のトラウマや身体的なコンプレックスが原因となっている場合、本人自身が気付いていないこともあります。ED治療薬で改善が見られない場合は、専門家の心理カウンセリングを受けるのも一つの方法です。
体の問題が引き起こすED(器質性ED)の主な原因は、血管の障害や神経の障害、男性機能の低下の3つです。
血管の障害は、加齢による動脈硬化や生活習慣病により引き起こされ、陰茎海綿体への血流を悪化させることで勃起に影響を与えます。
神経の障害は、てんかん・脳卒中などの疾患や、外科手術・事故による神経損傷が勃起を妨げる主な原因です。
男性機能の低下については、加齢や運動不足、睡眠不足によるテストステロンの減少が主な原因です。性欲低下や神経伝達物質の減少を引き起こし、EDのリスクを高めてしまいます。
器質性EDの改善には、原因となる疾患の治療が不可欠です。栄養バランスのとれた食事や適度な運動、睡眠時間の確保といった生活習慣の改善も重要な対策となるでしょう。
根本的な治療には時間を要するため、ED治療薬の併用も効果的です。ED治療薬の服用により勃起を繰り返すことで血流量が増え、EDの症状が改善されることがあります。
薬の影響によるED(薬剤性ED)は、精神安定剤や抗うつ薬、降圧剤といった医薬品の副作用で発症します。神経伝達やホルモンバランスに影響を与える薬剤によりEDの症状を引き起こすことがありますが、薬剤を服用してもすべての人がEDを発症するわけではありません。
薬剤性EDの対処法としては、EDを引き起こしにくい薬への変更や、投薬量の調整が考えられます。薬の変更や投薬量の調整を試みる際は、必ずかかりつけの医師に相談しましょう。自己判断での薬の変更・調整は、持病の治療そのものに悪影響をおよぼす恐れがあります。
EDにより生活の質が著しく低下していると感じるのであれば、ED治療薬の服用も視野に入れましょう。ED治療を検討する際は、服用中の薬とED治療薬の併用が可能であるか医師に相談してください。
混合性EDは、器質性・薬剤性・心因性の要因が複合的に作用して発症するEDです。高齢者に多く見られ、身体的な問題がきっかけとなり心理的な問題も重なるパターンが一般的です。
混合性EDの主な原因としては、加齢による動脈硬化や高血圧、仕事の責任増大によるストレス、家庭環境の変化(介護や子どもの自立など)、医薬品の副作用によるEDのトラウマなどがあげられます。
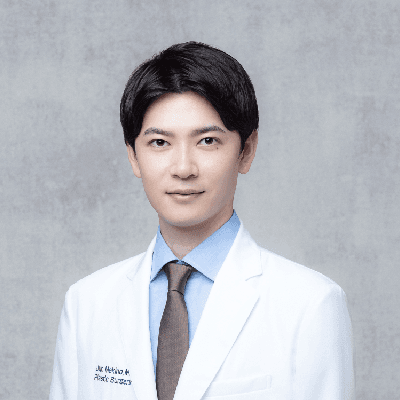
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
たとえば、加齢による身体的変化に不安を感じるとともに、仕事のストレスや家庭環境の変化が重なり、服用している薬の副作用でEDを経験するといったケースがあります。
混合性EDの対策としては、適度な運動・バランスのよい食事といった生活習慣の改善やストレス管理、医師への相談(薬の調整・ED治療薬の検討)などです。
身体面と心理面の両方にアプローチする総合的な対策が必要となるため、医師に相談して、適切な治療計画を立てましょう。
ED(勃起不全)は多くの男性にとってデリケートな問題ですが、効果的な対処法を実践することで改善が期待できます。ここでは、EDを克服するための具体的な方法・治し方を紹介します。
EDを引き起こす主な原因は、以下のとおりです。日常生活を見直すことで、改善を目指しましょう。
| 見直す項目 | 原因 |
|---|---|
| ストレス | 精神的なストレスが心因性EDを引き起こす |
| 喫煙 | 喫煙により血流が悪くなり、勃起しにくくなる |
| 飲酒 | 適量であれば問題ないが、過度な飲酒は勃起に悪影響を与える |
| 睡眠 | 睡眠時間が短いと体を十分に休められず、男性ホルモンの分泌が減少し、EDになりやすくなる |
まず、ストレス解消を図ることが大切です。過度なストレスは男性ホルモンの減少を招き、EDのリスクを高めます。体を動かす、好きな音楽を聴くなどしてストレス解消に努めましょう。
できる限り禁煙することも大切です。喫煙は血管内皮にダメージを与え、陰茎への血流を悪化させるためEDのリスクを高めます。
飲酒も適量にとどめることが重要です。過度な飲酒は肥満や動脈硬化につながり、EDを引き起こすおそれがあります。1日の適量を守り、深酒をした翌日は飲酒を控えるなど上手に付き合うことが大切です。
最後に、十分な睡眠時間の確保です。睡眠中にはテストステロンという男性ホルモンが多く分泌されるため、十分な睡眠はEDの改善・予防に役立ちます。6~7時間程度を目安に睡眠をとるよう心がけましょう。
EDの改善や予防には、栄養バランスのよい食生活が重要です。毎日3食、バランスの取れた食事を心がけることで、男性ホルモンの分泌が活性化し、勃起力や血流の改善が期待できます。
EDの改善効果が期待できる主な栄養素は、以下のとおりです。
| 栄養素 | 効果 | 含まれる食材 |
|---|---|---|
| 亜鉛 | テストステロンの分泌を促進する | 牡蠣、レバー、牛肉 |
| シトルリン | 血管拡張作用がある | スイカ、メロン |
| DHA、EPA | 血液をサラサラにする | 青魚 |
| ビタミンE | 血行促進作用がある | アーモンド、アボカド |
亜鉛やシトルリン、DHAなどの栄養素を意識的に摂取することで、EDの改善に役立つ可能性があります。
一方で、注意すべきは高カロリーの食事や動物性脂肪・コレステロールが多い食べ物です。これらは動脈硬化を引き起こし、血流を悪化させることでEDの原因となる可能性があります。
ED(勃起不全)の改善には、筋トレや運動が効果的です。EDの主な原因は血流の悪化であるため、筋トレや運動を行うことで血流が改善され、陰茎への血液供給の正常化が期待できます。
また、筋トレによってテストステロンの分泌を促進することも大切です。テストステロンは性欲や勃起力にかかわる男性ホルモンであり、筋肉を刺激することで増加します。テストステロンは20代をピークに減少し、50代以降には急激に低下するため、運動を習慣化することが重要です。
ED治療薬は、勃起をサポートする効果的な手段です。以下のED治療薬は一時的に血流を促進し、勃起を助けます。
| ED治療薬 | バイアグラ | シアリス | レビトラジェネリック |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 効果の強さや持続時間の長さは標準的 | 効果の持続時間が長い | 即効性があり、効果が強い |
| 効果の強さ | 強い | マイルド | とても強い |
| 食事の影響 | 食後に服用すると効果が減弱するので、空腹時もしくは食事から2時間程度空けて服用する | 食事の影響は受けにくい | バイアグラほど食事の影響は受けないが、空腹時もしくは食事から2時間程度空けて服用するのが望ましい |
| 副作用 | ・ほてり ・頭痛 ・鼻詰まり など | ・出にくい | ・ほてり ・頭痛 ・鼻詰まり など |
ED治療薬の服用を続けることで海綿体への血液流入が増加し、EDの症状改善を期待できるでしょう。
ED治療薬は、直接クリニックに行くほか、オンライン診療でも入手できます。オンライン診療では、自宅で診察を受けられるため、忙しくて通院に負担を感じる方やプライバシーを重視する方におすすめです。
診察予約や診察、治療薬の支払いがインターネット上で完結し、基本的に予約時間になるとすぐに診察が始まるため、時間を有効に使えます。
ED(勃起不全)は、心因性や器質性、薬剤性などさまざまな原因で発症しますが、適切な治療や生活習慣の見直しなどにより改善が期待できます。
日常生活のストレス管理や食事の栄養バランスなどを見直すとともに、必要に応じて医師の診察を受けてED治療薬を服用しましょう。直接クリニックに行くのが難しい人には、オンライン診療がおすすめです。
レバクリでは、EDのオンライン診療を行っています。場所や時間にとらわれずにビデオチャットや電話で診察が受けられ、処方された薬は自宅など好きな場所に届きます。診察料は無料なので、ぜひご予約ください。