更新日:2025年08月04日
インポとは、性機能全般の障害を指す広い概念です。ED(勃起不全)も含まれていましたが、現在では医療用語として使用されなくなりました。一方、EDは勃起機能の問題を指し、現代の医療用語として広く使われています。
本記事では、インポとEDの違いやEDの原因・治療方法について解説します。
「インポ」と「ED」は男性の性機能に関する用語ですが、その意味や使用される文脈に違いがあります。
インポは古くから使われてきた言葉で、より広範な性的不能を指しますが、差別的な意味合いを含むとされています。
一方、EDは医学的に定義された勃起機能の問題を指し、適切な表現として広く使用されています。
インポは性的不能を指す言葉で、現在の性機能障害(SD)に近い意味合いです。性欲・勃起・性行為・射精・オーガズムのいずれかが欠ける、または不十分な状態を指します。
かつては広く使用されていましたが、「役立たず」や「能力が低い」といった差別的な意味合いを含むため、現在ではほとんど使われていません。1995年に「日本インポテンス学会」が「日本性機能学会」と改名したことも、この変化を反映しています。
ED(勃起不全・勃起障害)は、勃起機能に関する問題に限定され、性欲や快感などは含まれません。EDは、満足な性行為を行うために十分な勃起が得られない、もしくは勃起を維持できない状態です。
「インポ」と混同されることもありますが、EDは勃起のトラブルに焦点を当てています。
EDの症状としては、以下の例が挙げられます。
これらの症状が続く場合、EDの可能性があります。EDは単なる性的な問題にとどまらず、身体的または心理的な要因が関係していることもあるため、症状に心当たりのある方は医師に相談してみましょう。
インポ(ED)の原因は多岐にわたり、心理的要因(心因性ED)や薬剤の副作用(薬剤性ED)、身体的要因(器質性ED)、複合的要因(混合性ED)が考えられます。EDの適切な治療には、その根本的な原因を検討することが重要です。ここでは、それぞれの原因について解説します。
心理的要因によるEDは、心因性EDと呼ばれます。心因性EDは、精神的なストレスや心理的な問題が原因となって発症します。
朝立ちや自慰行為時には正常な勃起が見られる場合、心因性EDの可能性が高いといえるでしょう。具体的な原因としては、以下の例が挙げられます。
これらの心理的要因は、性的刺激を脳に伝達する神経に支障をきたすこともあります。
薬の副作用がEDの原因となることがあります。薬剤によっては、中枢神経・末梢神経・循環器系・消化管などに作用し、勃起機能に影響を与える可能性があります。
以下の薬を服用中に勃起力の低下を感じた場合は、薬剤性EDの可能性が高いでしょう。
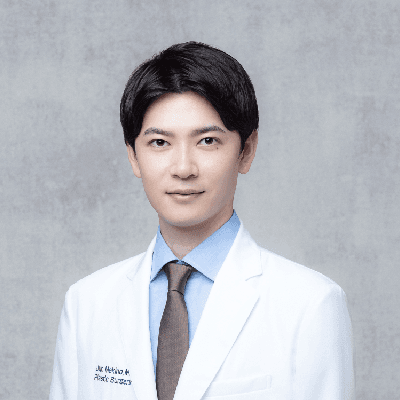
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
上記の薬以外にも、アレルギーの薬などがEDの原因となることもあります。ただし、EDへの影響を気にして自己判断で服用中の薬を中止・変更することは大変危険です。薬の服用に関しては、必ずかかりつけの医師に相談しましょう。
身体的要因によるED(器質性ED)は、主に血管や神経の障害が原因です。
血管の障害では、性的刺激を受けても陰茎海綿体に十分な血液が流れ込まないため、勃起が困難になります。主な原因は加齢による動脈硬化です。また、糖尿病や高血圧、高脂血症といった生活習慣病も血管の働きを妨げ、EDのリスクを高めます。
身体的要因によるEDは、50〜60代の方がなりやすいとされています。加齢や乱れた生活習慣が引き金となることも多く、年齢を重ねるにつれて勃起しづらくなった場合は身体的要因が考えられるでしょう。また、泌尿器系の病気や男性ホルモンの分泌量減少も、EDの原因となることがあります。
神経の障害は、脳出血・脊髄損傷・てんかん・パーキンソン病・アルツハイマー病などです。これらは、性的刺激の伝達を阻害し、勃起の信号が陰茎まで届かなくなる原因となります。
複合的要因によるED(混合性ED)は、身体的要因や心理的要因、薬剤の影響のいずれかが重なって発症するタイプです。40代以降の男性に多く見られます。
たとえば動脈硬化や高血圧などで血管にダメージを受け、同時に仕事のストレスや不安から心理的な負担が加わることで、EDが悪化するケースです。
このような場合、身体的な問題が根底にある一方で、性行為時における失敗がトラウマとなり、EDが進行してしまうこともあります。複数の原因によるEDの場合、どのような原因が主なのかを検討することはED治療において大切になります。
インポ(ED)は、適切な対策を講じることにより改善が可能です。ここでは、EDの主な改善策として生活習慣の見直しやED治療薬の服用、その他の治療法について解説します。これらの方法を組み合わせることでEDの症状改善を図りましょう。
EDの改善には、生活習慣の見直しが大切です。多くの場合、EDの背景には生活習慣病があります。ED治療薬による対症療法だけでなく、根本的な改善を図りましょう。
まず、食生活の改善です。栄養バランスのよい食事を心がけ、塩分の高い食事は控えましょう。塩分過多は高血圧を引き起こし、血流が悪くなってEDのリスクを高めてしまいます。また、暴飲暴食を避けることで、高血圧症や動脈硬化、糖尿病の予防にもつながるでしょう。
次に、適度な運動や十分な睡眠です。定期的な運動は男性ホルモンの分泌や血流を促進し、ED予防や肥満防止に役立ちます。さらに、十分な睡眠をとることで男性ホルモンの分泌を促し、EDの予防につながるでしょう。
ストレス管理も重要な要素です。日々のストレスが心因性EDの原因となることもあるため、運動する・好きな音楽を聴くなどして適宜ストレス解消を図り、溜め込まないよう心がけましょう。
飲酒や喫煙もできる限り控えることが大切です。適量の飲酒はリラックス効果をもたらす場合もありますが、過度な飲酒は中枢神経系や血流に悪影響を及ぼし、EDの原因となるおそれがあります。また、喫煙は血流を悪くしてEDのリスク因子となるため、禁煙をおすすめします。
ED治療において、治療薬の服用は主要な方法の一つです。ED治療薬は、性的興奮に伴い血管を広げることで勃起をサポートします。
心因性EDのケースでは、ED治療薬の服用により成功体験を得ることで、不安が解消されてEDの改善につながる可能性があります。薬剤性EDに関しても、服用中の薬と併用禁忌でなければ、ED治療薬の使用により改善が見込めるでしょう。
日本では、バイアグラ(シルデナフィル)やシアリス(タダラフィル)、レビトラ(バルデナフィル)が厚生労働省よりED治療薬として認可されています。ED治療薬は医師の処方が必要な医療用医薬品で、服用したい場合は医療機関での受診が必要です。
| ED治療薬 | バイアグラ(シルデナフィル) | シアリス(タダラフィル) | レビトラ(バルデナフィル) |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 効果の強さや持続時間の長さは標準的 | 効果の持続時間が長い | 即効性があり、効果が強い |
| 効果 | 強い | マイルド | とても強い |
| 食事の影響 | 食後に服用すると効果が減弱するので、空腹時もしくは食事から2時間程度空けて服用する | 食事の影響は受けにくい | バイアグラほど食事の影響は受けないが、空腹時もしくは食事から2時間程度空けて服用するのが望ましい |
| 副作用 | ・ほてり ・頭痛 ・鼻詰まり など | ・出にくい | ・ほてり ・頭痛 ・鼻詰まり など |
ネット通販で海外製のED治療薬が販売されていることもありますが、効果や安全性が保証されていない偽装品の可能性があるため、必ず医師の診察を受けて処方してもらいましょう。
インポ(ED)の改善に向けて、他にもいくつかの治療法があります。
まず、薬剤性EDが疑われる場合、かかりつけの医師への相談が大切です。服用中の薬を自己判断で中止すると、持病の治療に深刻な影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
次に、医療機関によっては陰茎への注射や補助具の使用による治療法もあります。ED治療薬を服用できない方や治療薬を服用しても効果が見られない場合の選択肢となります。
さらに、心因性EDと診断された場合は、心理療法が効果的なこともあります。専門家によるカウンセリングを通じて、心理的な要因の解消を目指します。
EDの診断や治療を受けるには、泌尿器科や内科、ED治療クリニックを受診するのが一般的です。
EDの原因となる病気や薬の副作用を見逃さないためにも、早めの受診をおすすめします。また、受診前にセルフチェックを行うことも一案です。EDの症状の程度を把握する際、国際勃起機能スコア(IIEF)の質問に答えた点数が参考になります。
直接クリニックに行って受診することに抵抗がある方は、オンライン診療の利用も検討してみましょう。オンライン診療であれば自宅で受診でき、薬は配送してもらえるためおすすめです。
インポやEDは、身体的・心理的な要因によって引き起こされるデリケートな問題ですが、正しい理解と適切な治療によって改善を図れます。
生活習慣の見直しやED治療薬の服用など、状況に応じた対策が効果的です。早めに医師に相談し、自分に合った改善策を見つけることが、充実した生活を取り戻す第一歩となります。
通院する時間がない方は、オンライン診療もおすすめです。
レバクリでは、EDのオンライン診療を行っています。ビデオチャットや電話で診察を受けられ、処方薬は自宅など希望の場所へ配送されます。診察料は無料なので、気軽に予約してみてはいかがでしょうか。