更新日:2025年08月04日
「彼氏がEDになり、どうすればよいかがわからない」「EDの対処法があれば知りたい」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。EDになる原因は主に心因性や体の不調によるもので、心因性の例には緊張やプレッシャー、ストレスなどが挙げられます。
本記事では、彼氏がEDになる原因や対処法、パートナーとしてどのように接すればよいかなどを解説します。
EDとは、満足な性行為を行うために十分な勃起が得られないこと、もしくは勃起を維持できない状態を指します。
勃起は、次のような流れで起こります。
このうち脳や血管、神経のどれかひとつでも不調があると勃起しづらくなり、EDになってしまいます。
ここでは、EDの主な原因についてみていきましょう。
EDの原因には、心因性と器質性、薬剤性が挙げられます。
心因性は、精神的・心理的な原因で勃起できないケースです。器質性は、加齢や血管・神経の障害、糖尿病・高血圧の生活習慣病など、身体的な原因によりEDを発症します。薬剤性は、薬の副作用により起こるEDです。
なお、心因性や器質性、薬剤性の原因が組み合わさって起こる混合性のEDもあります。たとえば、器質性のEDにより勃起できず、それがトラウマになって心因性EDも発症するという例が挙げられます。
全体的に多いのは混合性EDとされていますが、20代〜30代でEDになる場合の多くは心因性EDです。
勃起は脳や神経、血管の状態が関係する繊細な現象であり、心理的な影響を受けやすいでしょう。
心因性のEDの原因は、過去のトラウマやストレスなど人によりさまざまです。
具体例をみてみましょう。
過去に性行為でうまくいかなかったり、うまくできないことについてパートナーから何か言われたりした経験があると、それがトラウマになってEDになる場合があります。
失敗した経験がコンプレックスとなり、「またダメなのではないか…」という不安につながります。性行為のときに緊張やプレッシャーが生じ、EDになりやすいでしょう。
トラウマがなくても、経験が少ない場合は性行為をすること自体に緊張し、勃起できない場合もあります。また、女性に苦手意識がある場合や、幼少期の経験など本人も気づいていない潜在的な原因があって勃起できないケースもあります。
性行為がマンネリになっていたり、彼女に魅力を感じなくなっていたりして性的刺激を受けず、勃起できないケースもあります。また、けんかをして険悪な状態になっている場合も、性行為をする気持ちにはなりづらいでしょう。
職場の人間関係などでストレスや心配ごとを抱えていたり、疲れがたまっていたりすることも、EDになる原因のひとつです。性行為とは関連性のない原因ですが、ストレスや悩み、不安などが大きくなると、脳が性的興奮を感じにくくなってEDの症状が起こります。
彼氏がEDになっても、彼女である自分が原因とは限りません。むしろ他に原因があるケースも多く、自分が協力することでEDを治せる可能性もあります。
ここでは、彼女ができるEDへの対処法を紹介します。
EDに対して適切に対応するためには、彼氏・彼女のどちらも正しい知識を身につけることが大切です。彼氏が知識不足の場合は、彼女が知識を身につけておくことで、足りない部分を補えます。
ED対策で身につけたい知識は、以下のとおりです。
まず、勃起してもEDの場合があることを知っておきましょう。EDかどうかは、勃起したときの硬さや維持力で判断できます。勃起してもやわらかいときや、以前より明らかに硬さが減っている場合はEDに該当する可能性があります。
また、勃起しても挿入前に萎える、挿入しても射精に至る前に萎えるなど、性行為が満足にできない状態もEDに含まれると考えてよいでしょう。
EDの患者は40歳以上が多く、年代が上がるほど有病率は上がります。しかし、20代〜30代であってもEDになる可能性はあります。
EDの原因は器質性だけ、心因性だけといったケースは少なく、多くが混合性とされています。混合性の場合、主な原因を検討し改善を図ることはED治療にとって大切になるため、クリニックで受診して医師に相談するとよいでしょう。
EDの治療はオンライン診療でも行えるため、病院に行くことをためらっている場合は活用するとよいでしょう。
彼女がEDを受け入れる姿勢を示すことで、彼氏のEDが改善する可能性があります。
彼氏は自信を失っている可能性があり、満足のいく性行為ができないことを彼女が責めてしまうと、追い打ちをかけることになります。EDは心理的な影響も大きいため、さらに勃起できない状態になってしまうかもしれません。
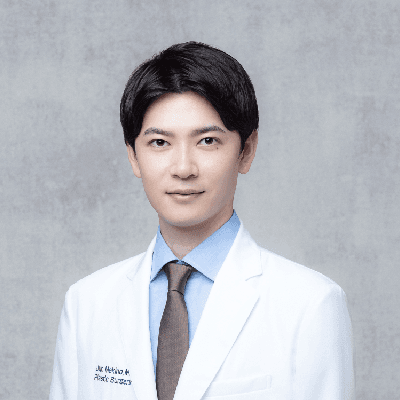
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
彼女が受け入れる姿勢を見せて寄り添うことで、彼氏を安心させられます。リラックスした状態になれば、改善に向かう可能性があるでしょう。
勃起は繊細な現象で、健康状態も大きく影響します。生活習慣が乱れて血管の状態が悪くなると、器質性EDになりやすくなります。
不規則な生活や乱れた食生活など、生活習慣がよくないと考えられる場合は、見直すようにアドバイスするとよいでしょう。生活習慣の改善によって健康状態がよくなれば、EDが改善される可能性があります。
また、生活習慣の乱れはEDだけの問題にとどまらず、生活習慣病をはじめとする疾患を引き起こします。EDは、何らかの病気のサインかもしれません。早めに改善できるよう働きかけましょう。
EDの原因がマンネリによるものと思われる場合は、これまでと違うシチュエーションで新しい刺激を生み出してみると、効果が出るかもしれません。
たとえば、次のような工夫が挙げられます。
ちょっとした変化でもよい刺激となり、EDの改善につながる可能性があるでしょう。
ストレスや仕事の疲れなどが原因と考えられるときは、2人で一緒に取り組める対策がおすすめです。
たとえば、次のような取り組みが挙げられます。
運動や料理は、前に説明した生活習慣の改善にもつながります。一緒に取り組むことで、2人の関係性も深まるでしょう。
EDを根本的に治療するためには、原因の解消を図ることが大切です。心因性の原因が多いとはいえ、器質性の可能性もあります。病院を受診すれば原因がわかり、適切な治療ができるでしょう。
病院での主な治療は、ED治療薬の服用です。ED治療薬は血管を広げて血流を増やし、勃起を助ける薬で、バイアグラやシアリス、レビトラなどの種類があります。これらのED治療薬はオンライン診療でも処方してもらえるため、一度受診してみるとよいでしょう。
彼女がEDへの対策に関わる場合、彼氏がEDに対してどのように向き合っているかで対応は異なります。
それぞれみていきましょう。
彼氏がEDを自覚して積極的に対策している場合、彼女は基本的に見守りの姿勢で問題ありません。自分もEDを受け入れる姿勢を見せ、寄り添って見守りましょう。
ただし、彼氏が自力で治そうとしてうまくいっていない場合は、病院の受診や治療薬の服用を提案してみるなど、背中を押すことも大切です。
病院に一緒に行くなどして、治そうと頑張っている彼氏を支えましょう。
EDを自覚しているものの行動しない彼氏には、EDに関する正しい知識を伝え、治療に前向きになるよう働きかけましょう。EDは珍しいことではなく、多くの男性が悩んでいることや、EDは適切な対応により治せることを伝えましょう。自分も協力するという姿勢を見せ、一緒に対策を考えます。
いくつかの対策を提案し、彼氏が受け入れるものがあれば、治療に向けた行動をサポートしましょう。
彼氏が性行為の話題を避け、EDへの対策から目をそむけようとしている場合、まずは関係を改善することからはじめましょう。何でも本音を話し合える関係を築き、EDについてどのように考えているのか、自分から話してもらえる関係性を築きます。
彼の本音を聞けたら、その気持ちに共感を示し、「対策してくれたら自分も協力したい」ことを伝えましょう。
EDに関する話題を避ける彼氏とは、どのように接すればよいのか迷うことがあるかもしれません。
ここでは、EDの彼氏への接し方を解説します。
EDの彼氏は自信を失い、悩んでいる可能性が高いと考えられます。しかし、彼女に対して本音を語らない男性もいるでしょう。
EDについて話をしたがらない彼氏には、その気持ちに寄り添い、本音を打ち明けてもらうようにすることが大切です。
性行為に対して自信がなかったり、緊張やプレッシャーを感じたりしている場合、彼女から気にしていないことを伝えれば、不安を解消できるかもしれません。過去のトラウマがある場合も、打ち明けてもらうことで、解決に向けた行動をとれます。
ただし、関係が悪化してしまう可能性があるため、無理に聞き出すことは避けましょう。まずは、彼氏が自分から自然に話してくれるような関係性を築くことが大切です。
EDの原因がわからないと、彼女は自分のせいだと考えてしまうかもしれません。だからといって、彼氏の愛情を疑うような発言は避けましょう。彼氏自身もEDに悩み、彼女に対して申し訳ないと思っている可能性があります。
相手を非難する言動をすれば、さらに彼氏を傷つけてしまうでしょう。非難されることで、彼氏は性行為へのプレッシャーが高まり、EDが悪化するおそれもあります。
20代~30代の男性のEDは心因性のケースが多く、彼女の協力によって改善を図れる可能性があります。EDを受け入れ、彼女が協力する姿勢を示せば、彼氏も安心するでしょう。
EDの対策には生活習慣の改善や新しい刺激を試すなどの方法がありますが、より効果的に治療したい場合には、病院で受診し、ED治療薬を服用するのも一つの方法です。
「彼氏が病院に行くのをためらっている」という場合は、オンライン診療をすすめてみてはいかがでしょうか。
レバクリのオンラインED診療であればビデオチャットや電話で診察が受けられ、処方された薬は自宅など好きな場所に届きます。診察料は無料のため、ぜひ利用してみてください。