更新日:2025年09月03日
勃起しなくなった場合には、ED(勃起不全・勃起障害)が疑われます。EDには器質性EDや心因性EDなどがあり、それぞれ原因によって改善方法が異なります。
この記事では、勃起しなくなった場合に疑われるEDの種類や症状のほか、勃起しなくなったときに試したい勃起力を高める方法などについて解説します。
勃起しなくなった場合に考えられる原因として、ED(勃起不全・勃起障害)が挙げられます。ED(Erectile Dysfunction)とは、性交時の勃起や勃起状態の維持が困難で、性行為を満足に行えない状態のことです。
勃起は、陰茎にある海綿体が硬くなることで起こります。海綿体とは細い血管が多く集まったもので、通常は海綿体につながる血管や平滑筋と呼ばれる筋肉が収縮している状態です。
しかし、性的興奮や刺激が加わると、脳の中枢神経から陰茎へ興奮が伝わり、海綿体につながる血管や平滑筋が緩んで血液が大量に流れ込みます。すると、大量に流れ込む血液の圧力によって、海綿体が硬くなり、勃起するという仕組みです。
勃起すると海綿体の膜が腫れた状態になるため、勃起が維持されます。
勃起には、勃起の指示を伝える神経と勃起を引き起こす血管の2つが関係しています。2つのうちどちらかが支障をきたすと、勃起しづらい・勃起を維持できないといったEDの症状が起こります。
EDを引き起こす原因は、次のようなものです。
EDは、単独の原因で引きこされることは少なく、むしろ複数の原因が重なっている場合が多いとされています。
EDは、まったく勃起しない状態だけを指すわけではありません。ほかにも、下記がEDの症状として挙げられます。
朝立ちしないことは、EDの初期症状といわれています。
通常、男性は睡眠時に性的興奮とは関係なく自然現象として勃起を繰り返しています。そのなかで、ちょうど目覚める直前に起こった勃起が朝立ちになります。
EDになると勃起力が衰えて朝立ちが起こりにくくなるため、EDの初期症状といわれています。
EDには4つの種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
器質性EDとは、身体的な要因がきっかけで起こるEDのことです。勃起は神経や血管の働きと密接な関係があり、それらの働きが悪くなると、正常に勃起できなくなります。神経や血管の働きが低下する原因の例は、以下のとおりです。
これらは、加齢や生活習慣の乱れなどが原因で起こるケースが多いとされています。年齢を重ねて勃起しなくなったという場合は、器質性EDが疑われます。器質性EDは、病気やケガが原因で起こるEDであるため、改善には病気そのものの治療や改善が必要です。
心因性EDとは、精神的ストレスやトラウマなどが原因で引き起こされるEDです。原因としては、次のようなものがあります。
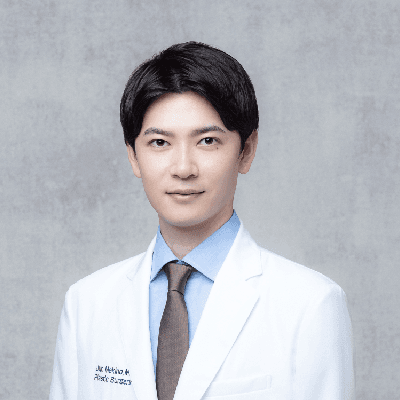
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
自分の両親から孫を望まれることによるプレッシャーや、性交渉で失敗したトラウマなども該当します。自慰行為では勃起するものの、パートナーとの性行為では勃起しない場合は、心因性EDの可能性があるでしょう。
心因性EDの場合、ストレスの軽減やパートナーとの関係改善などが大切です。
服用している薬剤の副作用で発症したEDが、薬剤性EDです。たとえば、次のような薬剤を継続的に服用中で「勃起しなくなった」と感じている場合は、薬剤性EDが疑われるでしょう。
| 薬の種類 | 薬剤名 |
|---|---|
| 降圧剤 | ・利尿薬 ・β遮断薬 ・カルシウム拮抗薬 |
| 抗うつ薬 | ・選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI) ・セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI) ・三環系抗うつ薬 |
| 前立腺肥大症治療薬・薄毛治療薬 | ・5α還元酵素阻害薬 |
混合性EDとは、器質性EDや心因性ED、薬剤性EDのいずれかが合わさって起こるEDのことです。
たとえば、加齢や生活習慣の乱れによって器質性EDの原因となる動脈硬化が起こり、心因性EDの原因であるストレスも合わさって、勃起しづらくなることがあります。混合性EDは、40〜60代の人に多いのが特徴です。
ここでは、勃起しなくなった場合に試したい、勃起力を高める方法を5つ紹介します。
勃起力は、血流やホルモン分泌が大きく影響しており、食生活の改善が効果的です。栄養バランスのとれた食事を心掛けつつ、EDの予防・改善に効果が期待できる栄養素を積極的に摂取するとよいでしょう。
「勃起しなくなった」と感じている場合に積極的に摂取したい栄養素の例は、以下のとおりです。
| 栄養素 | 役割 | 食材の例 |
|---|---|---|
| 亜鉛 | テストステロンの分泌を促す | チーズ・牡蠣・豚肉 |
| アルギニン | 成長ホルモンの分泌と血管拡張を促す | 鶏肉・エビ・大豆・マグロ |
| シトルリン | NO(一酸化窒素)の生成を促進し、血管を拡張する | スイカ・メロン・キュウリ |
| DHA・EPA(青魚に含まれる必須脂肪酸) | 血液をサラサラにする | サンマ・イワシ・サバ |
| ビタミンD | 不足すると、勃起不全になるリスクが高まる恐れがある | サケ・干ししいたけ |
栄養バランスのよい食事は生活習慣病の予防にもつながるため、肉・魚・野菜・果物・豆類などを1日の中でまんべんなく食べることを心掛けましょう。
勃起力を維持するには、適度な運動も大切です。「勃起しなくなった」「勃起力を向上させたい」という方におすすめなのは、次の4つです。
それぞれ見ていきましょう。
ケーゲル体操とは、アメリカ人の産婦人科医アーノルド・ヘンリー・ケーゲル氏が考案した運動のことです。ケーゲル体操によって骨盤底筋を鍛えることで、排便や排尿、勃起などのコントロール強化につながります。「勃起しなくなった」「勃起力の低下が気になる」といった場合は、下記の流れで毎日10分程度ケーゲル体操を行うとよいでしょう。
1日10セット程度を目安にケーゲル体操を継続すると、骨盤底筋が鍛えられ、陰茎の硬さや勃起持続力の向上を図れます。
開脚ストレッチも、勃起力改善には効果的です。骨盤周辺の筋肉が柔らかくなることで陰茎に血液が流れやすくなり、勃起力改善の効果が期待できます。普段、デスクワークが多い人やほとんど運動をしない人は、下記の開脚ストレッチで筋肉をほぐしましょう。
血行がよいお風呂あがりなどに行うと、より効果的です。
勃起力の改善には、ジョギングやランニングなどの有酸素運動もおすすめです。
有酸素運動は血液循環の促進に効果的なため、EDの原因となる動脈硬化の改善が期待できるでしょう。
また、ジョギングやランニングは全身運動であり、下半身・体幹の筋肉強化につながるほか、脂肪燃焼による生活習慣病のリスク低減効果も期待できるでしょう。
「勃起しなくなった」と感じている方が勃起力を高めるには、筋トレもおすすめです。筋トレには男性ホルモンの一種であるテストステロンの分泌を促す効果があり、テストステロンが増えることで勃起力の向上やED改善が期待できます。
とくにおすすめなのは、下記のような下半身の筋トレです。
下半身の筋トレを行うと、骨盤周辺の血流が改善され、EDの改善につながると考えられています。
睡眠時間が不足していると、男性ホルモンの分泌量が低下し、勃起力も低下しやすくなってしまいます。人によって必要な睡眠時間は異なりますが、1日6〜7時間程度を目安に睡眠時間を確保しましょう。
また、睡眠の質を高めるために、寝る前にスマートフォンを見ないことや、ゆっくりと入浴して血流をよくするなどの工夫も大切です。
タバコやアルコールは勃起力低下の一因とるため、「勃起しなくなった」と感じている場合は、できる限り禁煙・禁酒することがおすすめです。
タバコには、血流を悪くしたり血管を損傷したりする成分が含まれています。また、健康面から見ても、喫煙にはメリットがありません。
アルコールは、適量であればリラックス作用があるため、性行為前に少し飲む程度であれば問題ありません。
ただし、飲み過ぎはEDの原因となる動脈硬化や肥満を引き起こすリスクがあります。過度な飲酒をしないよう気を付けましょう。
食生活の改善や運動などを実践しても勃起力が変わらない場合は、ED治療薬の服用を検討しましょう。
ED治療薬は、性的刺激を感じた際に血流を促進し、陰茎の海綿体に血液が流れ込みやすい状態をつくります。ED治療薬を服用したい場合は、医療機関での受診が必要です。
「クリニックへ行きたいけれど通院時間がとれない」という場合は、オンライン診療を利用する方法もあります。オンライン診療のメリットは、次のような点です。
「勃起しなくなったから治療を受けたい」と考えているものの、通院時間がとれない場合や受診時に知り合いに会わないか不安な方は、オンライン診療の利用を検討してみましょう。
勃起しなくなった場合には、EDの可能性があります。EDには原因によって4種類あり、それぞれ改善方法が異なるため、自分がどのタイプなのかを見極めることが大切です。
勃起力を高める方法には、食生活の改善や運動、睡眠時間の確保、禁酒・禁煙などがあります。これらを試してみて効果が得られない場合は、ED治療薬の服用がおすすめです。ED治療薬は、医療機関で処方してもらえます。
通院する時間がない、人目を気にせず受診したいという場合は、オンライン診療の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
レバクリでは、ED治療薬のオンライン処方を行っています。オンライン診療では場所や時間にとらわれずにビデオチャットや電話で診察が受けられ、処方された薬は自宅など好きな場所に届きます。診察料は無料なので、ぜひご予約ください。