更新日:2025年09月03日
フケが止まらないと感じ、原因や対処法が気になっている方もいるでしょう。フケが止まらないのは、皮脂の過剰分泌や頭皮の乾燥のほか、病気が原因の場合があります。
この記事では、フケを引き起こす2つの原因とセルフケアについて解説します。また、フケが止まらないときに考えられる病気と、AGAとの関連性も紹介します。フケが止まらないことに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
そもそもフケとは、古くなった頭皮の角質が剥がれ落ちたもののことです。
人間の皮膚は、約4~6週間のサイクルでターンオーバーします。皮膚の一部である頭皮も、約4~6週間ごとに生まれ変わり、その際に剥がれ落ちた古い角質がフケと呼ばれます。
そのため、フケは誰にでも生じる生理的な現象です。ただし、頭皮の状態が良い方は、フケの大きさが小さく髪の毛を洗ったときに流れ落ちることから、それほど気になりません。
一方、なんらかの原因により頭皮にトラブルを抱えていると、フケの量が増えたり目立つ大きさになったりすることで、気になるようになります。
フケを引き起こす主な原因は、皮脂の過剰分泌と乾燥です。どちらが原因かによって、症状が異なります。
ここでは、フケを引き起こすそれぞれの原因について見ていきましょう。
フケを引き起こす要因の1つが、皮脂の過剰分泌です。皮脂が過剰に分泌されると、頭皮の常在菌であるマラセチア菌が増殖し、炎症を起こして脂性フケが大量に発生します。脂性フケの特徴は、以下のとおりです。
脂性フケが発生する主な要因は、ストレスです。心身がストレスを感じることで自律神経が乱れ、皮脂の分泌が増えると、脂性フケが発生します。
そのほか、脂質の多い食生活も脂性フケが発生する要因となります。
乾燥も、フケを引き起こす要因です。乾燥により頭皮のターンオーバーのサイクルが乱れると、未熟な角質細胞(垢)もはがれ落ち、乾性フケが増加します。特に、元々乾燥肌の方は、乾性フケが発生しやすくなるでしょう。
乾性フケの特徴は、以下のとおりです。
乾性フケが発生する主な要因には、以下が挙げられます。
乾性フケは、頭皮が乾燥することで発生しやすくなります。そのため、過度な洗髪やドライヤーによる乾燥のし過ぎは、乾性フケが発生するリスクを高めるでしょう。また、冬の乾いた空気も、乾燥フケを引き起こす要因となります。
ここからは、フケの軽減が期待できるセルフケアを紹介します。フケは、生活習慣や日々の行動を見直すことで、改善できる場合があります。
フケが止まらないと感じている方は、ここで紹介する内容を実践し、症状の改善を図りましょう。
フケが止まらないときのセルフケアの1つ目は、正しい方法でシャンプーをすることです。洗い残しやシャンプーのすすぎ残しがあると、脂性フケが発生します。また、洗い過ぎは乾性フケの要因となります。
フケの発生を抑える正しいシャンプーの手順は、以下のとおりです。
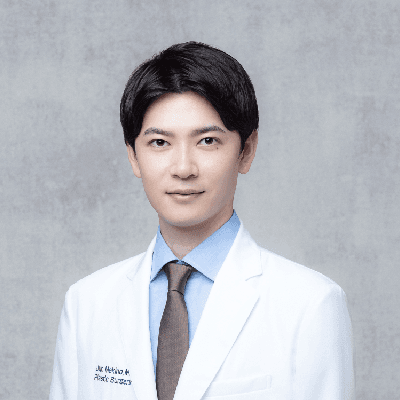
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
シャンプーをする際は、髪の毛だけでなく頭皮の汚れも落とすようにしましょう。爪を立てず、マッサージするようにやさしく洗髪することで、頭皮に傷が付くのを防げるほか、血行改善によるフケの改善も期待できます。
フケが止まらないときは、生活習慣を改善することも大切です。生活習慣の見直しの一例を、以下で確認しましょう。
生活習慣を見直すことで自律神経が整えば、頭皮環境の改善とターンオーバーの正常化が期待できます。ターンオーバーが正しいサイクルで起こるようになれば、過度なフケの発生を防げるでしょう。
フケが止まらないときは、バランスの良い食事をとることも大切です。また、脂性フケを軽減するには、脂質や糖質を多く含む食事はできる限り避け、頭皮環境の改善のために良質なタンパク質やビタミン類を積極的に摂取しましょう。
フケが止まらないときは、休息をとりストレスを解消することも大切です。過労や心労などにより心身にストレスがかかると、頭皮のターンオーバーが乱れてフケが増えることがあります。
心身の疲れを感じたら、ストレス過多になる前に十分な休息をとりましょう。ストレスによる自律神経の乱れを防止できれば、頭皮の正常なターンオーバーとフケの軽減が期待できます。
ここでは、フケが止まらないときに考えられる病気を4つ紹介します。
フケはセルフケアで改善できる場合もありますが、「セルフケアを試してもフケが改善しない」「生活に気を付けているのにむしろ酷くなった」というときは、病気が原因の可能性があります。
フケが止まらない状態が続き、症状に不安がある方は、医師の診察を受けましょう。
フケが止まらないときに考えられる病気の1つが、脂漏性(しろうせい)皮膚炎です。
脂漏性皮膚炎では、頭皮の常在菌であるマラセチア菌が大量に繁殖し、多くのフケを発生させます。脂漏性皮膚炎を引き起こす主な要因は、食生活の乱れやストレス、頭皮の汚れです。
脂漏性皮膚炎の治療では、マラセチア菌の繁殖を抑えるための抗真菌薬(外用薬)が処方されます。炎症が酷いときは、ステロイド外用薬が使われることもあります。
粃糠性(ひこうせい)脱毛症も、フケを発生させる病気の1つです。粃糠性脱毛症では、カサカサとした乾性フケが大量に発生し、フケが止まらないと感じる可能性があります。また、フケが毛穴をふさぐことで、脱毛を招きます。
粃糠性脱毛症を発症する主な要因は、不規則な生活や食生活の乱れ、ストレスです。治療では、まずステロイド外用薬で頭皮の炎症を抑えます。頭皮の炎症が落ち着き、フケが出る原因がマラセチア菌の増殖である場合には、抗真菌薬(外用薬)を併用することもあります。
フケが止まらないと感じる場合、乾癬(かんせん)が原因の可能性もあります。乾癬とは、身体の皮膚が赤くなって盛り上がり、かさぶたができる病気のことです。特に、頭皮や生え際は発生しやすいといわれています。
体質やストレスなどが発症の一因といわれていますが、明確な原因は解明されていません。主にステロイド外用薬で炎症を抑えながら、医師と相談して適切な治療を行うことが重要です。
白癬(はくせん)は、白癬菌に感染することで発症する病気です。頭皮に感染した場合の症状としては、カサカサとした大量のフケや抜け毛、切れ毛があります。レスリングや柔道など身体接触の機会が多く、マットに頭をこすりつけるスポーツをする方は罹患しやすい点が特徴です。
白癬の治療には、内服の抗真菌薬を用います。症状によっては、外用薬を併用することもあるでしょう。治療期間は数ヶ月ほどになるとされています。
フケが止まらない原因の1つである脂漏性皮膚炎は、AGAを併発するケースがあります。
脂漏性皮膚炎は、AGAを引き起こす直接的な原因にはなりません。ただし、脂漏性皮膚炎によって頭皮に炎症が起こると、脱毛につながるおそれがあります。
また、脂漏性皮膚炎を引き起こす乱れた生活習慣は、AGAの発症にもつながります。フケが止まらないだけでなく、抜け毛などの症状が気になる方は医師に相談しましょう。
医師に相談したいものの、日々の生活や仕事が忙しく通院の時間がとれない方もいるかもしれません。そのようなときは、場所や時間にとらわれず電話やビデオチャットで医師の診察を受けられるオンライン診療を、ぜひ活用してみましょう。
フケが止まらないときには、頭皮のターンオーバーが乱れている可能性があります。フケが止まらない症状を改善したいときは、まずは生活習慣やシャンプーの見直しなど、セルフケアを行ってみましょう。
セルフケアを実施してもフケが止まらないときは、病気が原因の可能性もあります。症状が心配なときは、速やかに医師の診察を受けましょう。
また、フケが止まらないだけでなく、抜け毛の症状がある方は、AGAを併発している可能性もあります。不安を感じる方は、医師に相談しましょう。
AGAの診察を希望する場合は、オンライン診療のレバクリがおすすめです。レバクリであれば、場所や時間にとらわれず、電話やビデオチャットで医師の診察を受けられます。仕事が忙しく通院が難しい方や、近くに皮膚科やAGAのクリニックがない方は、ぜひレバクリでの受診を検討してみてください。