更新日:2025年10月30日
「ナイトキャップははげる原因になる?」と気になっている方もいるかもしれません。ナイトキャップは寝ている間の髪へのダメージを軽減する効果が期待できますが、誤った被り方をしていると逆効果となり、はげる原因になる可能性があります。
本記事では、ナイトキャップが与える薄毛への効果や逆効果になる被り方、使用時の注意点について解説します。ナイトキャップの正しい被り方を知って、適切に薄毛対策を行いましょう。
近年女性を中心に話題となっているナイトキャップですが、男性の薄毛対策にも効果的です。ナイトキャップの薄毛への効果について、見ていきましょう。
寝ている間、髪は頭の重さと枕の反発力によって常に圧迫された状態です。そのため、寝返りを打つたびに枕やシーツに髪がこすれ、知らず知らずのうちにダメージを受けてしまいます。さらに、髪同士が絡まり、引っ張られることで切れ毛や抜け毛の原因となることも少なくありません。
ナイトキャップを被ることで、動いても髪型を保てるため、寝返りによる摩擦や絡まりを軽減できます。とくにシルク素材のナイトキャップは、髪の表面をなめらかに保ち、摩擦を抑える効果が期待できます。
寝室や寝具は、こまめに掃除や洗濯をしても完全にホコリを排除することは難しいものです。とくに枕や布団には、目に見えないホコリや皮脂汚れ、ダニの死骸などが付着している場合があり、知らないうちに髪や頭皮に悪影響を及ぼしかねません。
ナイトキャップを着用することで、枕やシーツに付着したホコリや汚れが髪・頭皮に付着するのを防ぎ、清潔な状態を維持しやすくなります。また、空気中に舞っている微細なホコリや花粉などの付着も防げるため、敏感肌や頭皮のかゆみに悩む方にもおすすめです。さらに、ナイトキャップは寝具に潜むダニや、夏場の蚊などの虫から頭部を保護する役割も果たします。
ナイトキャップは、寝ている間に頭皮や髪の乾燥を防ぐ効果があります。とくに、エアコンを使用する頻度が多い夏や冬は、空気が乾燥しやすく髪や頭皮の水分が奪われやすいでしょう。その結果、髪がパサつき、切れ毛や枝毛が増えることで、抜け毛につながる可能性があります。また、頭皮が乾燥してかゆみが生じると無意識に頭を掻いてしまい、頭皮に傷ができたり、炎症を引き起こしたりすることもあるでしょう。
ナイトキャップを使用すれば、髪全体をカバーし、適度な湿度を保ちながら乾燥を防ぐことが可能です。寝ている間に無意識に掻いてしまっても、頭皮に直接触れずに済むため、頭皮に傷ができるリスクも軽減できます。
ナイトキャップは、正しく使えば薄毛対策になります。しかし、誤った被り方をすると、頭皮や髪への負担になり、はげることにつながりかねません。ナイトキャップが逆効果になる被り方について、解説します。
ナイトキャップを髪が濡れたまま被ると、逆効果になることがあります。濡れた髪は、キューティクルが開いて非常にデリケートなため、ダメージを受けやすい状態です。髪が濡れたままナイトキャップを被ると、髪の水分やタンパク質が失われやすくなり、パサつきやうねり、枝毛の原因になります。
さらに、ナイトキャップ内に湿気がこもると、雑菌が繁殖しやすい環境になります。頭皮に雑菌が増えると、かゆみやフケが発生しやすくなり、頭皮トラブルが発生することもあるでしょう。
ナイトキャップのサイズ選びを間違えてしまうと、薄毛対策に対して逆効果になったり、本来の効果を得られなくなったりするため注意しましょう。頭に対して小さすぎるナイトキャップを使用すると、ゴム紐の締め付けによって頭皮の血流が悪くなり、髪の成長に必要な栄養が十分に行き渡らなくなるリスクがあります。
一方で、大きすぎるナイトキャップを選ぶと、寝返りを打ったときにずれて脱げやすいでしょう。また、キャップの中で髪が動きやすくなり、摩擦が増えてキューティクルが傷ついたり、髪をまとめる効果が薄くなったりします。
通気性が悪い素材のナイトキャップを選ぶと、着用中に蒸れが発生し、頭皮環境を悪化させる原因になります。とくに高温多湿の時期は皮脂や汗の分泌が活発になるため、頭皮が蒸れやすいでしょう。頭皮が蒸れて頭皮環境が悪くなると、健康な髪の成長が妨げられ、抜け毛や薄毛のリスクを高める可能性があります。また、頭皮に細菌が繁殖し、ニオイやかゆみを引き起こす場合も少なくありません。
髪や頭皮に負荷をかけた状態でナイトキャップを被ると、逆効果になるかもしれません。とくに、オールバックのように髪を強く引っ張った状態では髪や頭皮に負荷がかかり、抜け毛の原因になります。さらに、寝ている間に頭を動かすことで、ナイトキャップの中で髪が締め付けられ、より強い摩擦や圧力がかかることもあるでしょう。「ナイトキャップではげることを避けたい」という場合には、髪への負荷をチェックすることが大切です。
薄毛対策としてナイトキャップを購入・使用するときは、以下の注意点を押さえましょう。
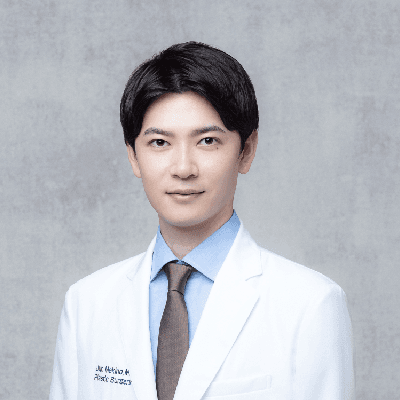
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
それぞれの注意点について解説します。
ナイトキャップを薄毛対策として使用する場合、シルクやコットン素材のものを選ぶとよいでしょう。
シルクは湿気を適度に吸収して外に逃がす働きがあるため、寝ている間の蒸れを防ぎつつ、髪の水分を守る効果を期待できます。表面がなめらかで摩擦が少なく、髪の毛の乾燥やキューティクルのダメージを抑えられるのも特徴です。コットンは通気性が高く、夏場の使用に適しています。耐久性に優れ、洗濯を繰り返しても傷みにくいため、長期間使用することが可能です。
加えて、ナイトキャップを選ぶときは、寝返りを打っても脱げない程度の大きさで、締め付けが強すぎないものを選びましょう。また、ゴムや紐でサイズ調整できるタイプを選べば自分の頭の大きさに合わせられるため、「サイズが合わずに脱げてしまう」「締め付けが強い」といった失敗を防げます。
ナイトキャップを被る前に、髪をしっかり乾かしましょう。とくに、お風呂上がりにナイトキャップを被る習慣がある方は注意が必要です。タオルドライだけでは髪の内部に水分が残りやすいため、ドライヤーを使って、毛先から根元まで乾燥させることを心がけましょう。
また、髪が長い方は乾かした後にブラッシングをして毛流れを整えることで、ナイトキャップ内での摩擦を減らし、髪への負担を軽減できます。とくに絡まりやすい髪質の方は、ナイトキャップを被る前に軽くオイルやヘアミルクをなじませると、髪のうるおいを保ちやすくなります。
ナイトキャップを長く清潔に使うためには、定期的に洗濯することが大切です。寝ている間、ナイトキャップには汗や皮脂が付着するため、洗濯せずに使い続けていると雑菌が繁殖しやすくなり、髪の毛や頭皮へのダメージにつながります。とくに、湿気がこもりやすい夏場や、髪に整髪料をつけたまま使用した場合は汚れが付着している可能性が高いため、こまめに洗濯しましょう。
ただし、ナイトキャップの素材によっては、洗濯方法に注意が必要です。たとえば、シルクはデリケートな素材であるため、手洗いやシルク専用の洗剤を使った弱水流での洗濯が適しています。洗濯後は、強く絞らずにタオルで水分を吸収させ、風通しのよい場所で陰干ししましょう。
薄毛に悩んでいる場合、ナイトキャップ以外にも効果的な対策があります。ここからは、ナイトキャップ以外の薄毛対策について解説します。
髪の健康を維持するためには、日々の栄養バランスを見直すことも大切です。食事に偏りがあると、毛根に十分な栄養が届かず、髪が細く弱くなりやすいでしょう。また、栄養不足になると頭皮のターンオーバーが乱れ、乾燥や皮脂の過剰分泌を引き起こし、健康な髪が育ちにくい環境になる可能性もあります。
薄毛対策で重視される栄養素は、「タンパク質」「ミネラル」「ビタミン」です。とくにタンパク質は髪の主成分であるケラチンの材料となり、健やかな髪の成長に大きく関わります。タンパク質が含まれているのは、肉や魚、卵、乳製品、大豆製品などです。タンパク質以外の栄養素もバランス良く摂取し、髪の成長を体の内側から支えましょう。
薄毛が気になる方は、日々のヘアケアの方法を見直してみるのもよいでしょう。
シャンプーをする際は、はじめにお湯で髪全体をしっかりすすぎ、汚れや皮脂を浮かせます。その後、シャンプーをしっかり泡立ててから、指の腹を使って優しく頭皮を洗いましょう。爪を立てたり、ゴシゴシと力を入れすぎたりすると頭皮を傷つける原因になるため気を付けてください。
洗髪時には、頭皮マッサージを取り入れるのも効果的です。指の腹を使って円を描くように優しく刺激すると、血行が促進されて毛根に栄養が届きやすくなります。
生活習慣の改善を行っても薄毛が改善しない場合や、すみやかに薄毛の悩みに対処したい場合は、AGA(男性型脱毛症)治療薬の服用も一つの方法です。AGAは進行性の脱毛症で、適切な治療を行うことで症状の進行を防ぎ、髪の成長をサポートできます。AGA治療薬には、大きく分けて「抜け毛を抑えるタイプ」と「発毛を促すタイプ」の2種類があります。自分の症状や目的に応じて、適した薬を処方してもらいましょう。
AGA治療薬は、病院に行くほか、オンライン診療で処方してもらえます。AGA治療薬はほかの薬との相互作用や副作用のリスクがあるため、服用中の薬がある方は受診時に医師に伝えましょう。
ナイトキャップは、寝ている間の髪へのダメージを軽減し、乾燥や汚れから髪や頭皮を守るアイテムです。しかし、誤った被り方をすると逆効果になり、はげる原因になることもあります。薄毛対策としては、ナイトキャップの活用に加え、栄養バランスの整った食事や適切なヘアケア、AGA治療薬の服用なども効果的です。
レバクリでは、AGAのオンライン処方を行っています。場所や時間にとらわれずにビデオチャットや電話で診察が受けられ、処方された薬は自宅など好きな場所に届きます。診察料は無料なので、ぜひご予約ください。