更新日:2025年08月04日
性行為の際に「硬さが足りない」」「勃起を維持しづらい」と感じ、EDの対策について気になっている方もいるかもしれません。EDの対策として、生活習慣の改善やED治療薬の服用などが有効です。
この記事では、EDの症状や原因、対策について解説します。ぜひ参考にしてください。
EDはErectile Dysfunctionの略で、勃起不全や勃起障害とも呼ばれています。EDは、満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られない、または維持できない状態が持続または再発することとされています。性行為のときに以下の状況が起こる場合は、EDの可能性があるでしょう。
EDについては、「EDとはどんな症状?原因別の治療方法からセルフケアについても解説」でも詳しく解説しています。
勃起が正常に起こるためには、以下の段階を経る必要があります。
性的な刺激を受けることにより脳の中枢神経が興奮し、その情報が脊髄神経を通ってペニスへ伝わり、海綿体に動脈血が多く流れ込みます。海綿体に動脈血が流れ込むと血液が充満し、海綿体は硬くなります。これが勃起のメカニズムです。EDは、この過程のいずれかに問題が生じることで起こります。
EDの主な症状として挙げられるのは、以下の6つです。
上記の症状がある場合、EDを発症している可能性があります。そのままにせず、早めに対策をとりましょう。
EDは、40歳を境に有病率が上がるとされています。現時点ではEDの症状がない人でも、年齢が上がるにつれ、勃起力が低下する可能性があるでしょう。
EDの原因にはさまざまなものがありますが、主に以下の4つに大別できます。
ここでは、それぞれの原因について解説します。
日常生活におけるストレスや性行為に対する不安、過去のトラウマなどの心理的要因によって引き起こされる勃起不全を、心因性EDと呼びます。精神的なストレスや不安を抱えている場合、性的興奮がうまくペニスに伝わらず、EDの症状が出ることがあります。心因性EDの主な原因として挙げられるのは、以下の5つです。
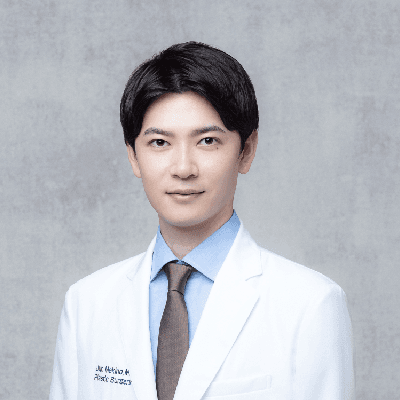
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
心因性EDは、20〜30代の比較的若い世代に多いEDです。オナニーをする際は問題なくても性行為のときに勃起しづらくなる場合、心因性EDの可能性があります。仕事のストレスやパートナーとの関係性などが原因の場合、ストレスの原因をできる限り取り除いたり関係改善を図ったりすることで、EDの症状が改善する可能性があります。
心因性EDについて詳しく知りたい方は、「心因性EDの原因は?治療方法や必要性についても解説」も参考にしてみてください。
血管・神経障害などの器質的な原因により引き起こされる勃起不全は、器質性EDと呼ばれます。勃起を引き起こすには、性的興奮が陰茎に伝わり、十分な量の血液を流入することが必要です。しかし、神経や血管に何らかの障害がある場合、陰茎に血液が流れ込まず勃起しづらくなることがあります。
器質性EDの主な原因として挙げられるのは、以下のとおりです。
高血圧や脂質異常症、肥満などは、偏った食事や運動不足といった生活習慣の乱れにより引き起こされやすくなります。
また、年齢が高くなると動脈硬化が起こる可能性が高まるため、動脈硬化によるEDの発生率も高くなると考えられています。
高血圧とEDの関係性については、「高血圧はEDを合併する可能性が高い?薬物療法や生活習慣についても解説」でも詳しく解説しています。
病気やケガの治療で使用する薬剤の副作用により、EDの症状が出る場合もあります。薬剤の副作用によるEDは、薬剤性EDと呼ばれています。副作用によってEDを発症する可能性のある薬剤の例は、以下のとおりです。
薬剤性EDは、薬剤の変更や減薬などにより改善する場合があります。しかし、そもそも薬剤による影響でEDなのか、治療中の病気によるEDなのかがはっきりしないケースもあります。例えば、高血圧の治療中で高血圧治療薬を服用しており、EDの症状が出ているケースです。
薬剤の副作用によってEDの症状が出ていると感じる場合、まずはかかりつけ医に相談するとよいでしょう。
心理的な原因と器質的な原因、薬剤の副作用のいずれかが重なって起こるEDを、混合性EDと呼びます。例えば、器質性EDで性行為に失敗した結果、それが不安やトラウマとなって心因性EDを引き起こす場合が挙げられます。
器質性EDや心因性ED、薬剤性EDが相互に影響しあっており、特にどの原因が主となるのかを検討することも治療においては大切になります。
EDになった場合、以下の対策を行うことにより改善される可能性があります。
ここでは、それぞれの対策について解説します。
EDの対策の一つ目は、定期的な運動です。運動不足の場合、EDの原因となる肥満や動脈硬化、男性ホルモン量の低下を引き起こす可能性があります。厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、習慣的な有酸素運動は肥満や脂質異常症、高血圧などの予防・改善に寄与するとされています。有酸素運動の例は、ジョギングやウォーキング、サイクリングなどです。
また、厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023(概要)」によると、健康づくりのために「息が弾み汗をかく程度以上の運動」を週に60分以上、筋力トレーニングを週に2~3日行うことが推奨されています。この時間を目安に、自身の生活習慣や身体の状況に合わせて運動や筋力トレーニングを実施するとよいでしょう。
なお、筋トレは血流を改善するほか、男性ホルモンのひとつであるテストステロンを増加させる効果が期待できます。おすすめの筋トレとして挙げられるのは、スクワットです。スクワットは太ももやお尻の筋肉を重点的に鍛えるため、下半身の血流を改善する効果が期待できます。
ただし、いきなり激しい運動や筋トレをはじめても、継続できなければ意味がありません。ウォーキングや簡単な筋トレなどからはじめ、継続的に取り組みましょう。
参考:厚生労働省「身体活動・運動の推進」
EDの対策の二つ目は、バランスのとれた食事をとることです。栄養バランスの偏った食生活が続くと、テストステロンの減少や血流の悪化につながり、勃起力が低下する恐れがあります。
EDの対策を行ううえで、塩分や糖質を摂りすぎないよう気を付けることが大切です。
厚生労働省の調査「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」によると、日本人男性の食塩摂取量の平均値は1日あたり10.7gです。一方、「『日本人の食事摂取基準(2025年版)』策定検討会報告書」によると、18~74歳の男性の場合、1日あたりの食塩摂取の目標量は7.5g未満となっています。食塩摂取量が多くなると、血管内の塩分を薄めるために血管内の水分が増え、高血圧を引き起こしやすくなるため、注意が必要です。
また、ファストフードやインスタント食品などには塩分や糖質が多く含まれており、頻繁に食べると肥満や高血圧、糖尿病などを引き起こすリスクもあります。栄養バランスの良い食事を摂るには、農林水産省の「ちょうどよいバランスの食生活」や厚生労働省・農林水産省の「食事バランスガイド」を参考にするとよいでしょう。
なお、栄養バランスのよい食事を心掛けつつ、勃起力の改善に役立つとされる栄養素を積極的に摂取するのもおすすめです。EDの対策に役立つとされる栄養素や食材の例は、以下のとおりです。
これらの栄養素を日常的に食事で摂取することが難しい場合は、サプリメントで補うのもひとつの方法です。
参考:
厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」
厚生労働省「日本人の食事摂取基準」
農林水産省「ちょうどよいバランスの食生活」
厚生労働省・農林水産省「食事バランスガイド」
EDの対策の三つ目は、質の良い睡眠をとることです。質の良い睡眠をとるために、以下のことを意識するとよいでしょう。
なお、EDの対策として睡眠時間を十分にとることも心掛けましょう。人によって必要な睡眠時間は異なりますが、厚生労働省「知っているようで知らない睡眠のこと」によると、働く世代に必要な睡眠時間は最低6時間で、6時間未満の睡眠は2型糖尿病やうつ病といった疾患のリスク増加と関連するとされています。1日に少なくとも6時間の睡眠をとることを意識しましょう。
参考:厚生労働省「知っているようで知らない睡眠のこと」
EDの対策のために、過度な飲酒や喫煙は控えましょう。アルコールには血管を拡張させる作用がありますが、過度に摂取した場合は血管が収縮するため、血流が悪くなるでしょう。血行不良になると、陰茎への血流が妨げられるため、勃起力の低下につながります。
厚生労働省「アルコール」によると、通常のアルコール代謝能を有する日本人が、「節度ある適度な飲酒」として1日平均で摂取してもよい純アルコール量は20g程度とされています。アルコールの過剰摂取により中枢神経が麻痺すると、陰茎への信号の伝達が妨げられて勃起しづらくなるため、アルコールの摂取量には注意しましょう。
また、たばこに含まれるニコチンや一酸化炭素には、血管収縮作用があります。喫煙による血管収縮や炎症によって動脈硬化を引き起こし、EDを発症する可能性があるでしょう。EDの対策をとるには、節酒や禁煙を心掛けることが大切です。
参考:厚生労働省「アルコール」
ストレスの解消も、EDの対策のひとつです。ストレスが原因で心因性EDを発症した場合、ストレスの原因をできる限り取り除いたり、ストレスを解消したりすることで症状が改善する可能性があります。ストレス解消法として挙げられるものは、以下のとおりです。
仕事が忙しく、リフレッシュするためのまとまった時間を確保できない場合、深呼吸する、好きなものを食べるなど短時間でもリラックスできる方法を見つけましょう。無理に趣味を見つけたり出かけたりする必要はなく、自分に合った方法でストレス解消を図ることが大切です。
ペニスのサイズや形を指摘されたり、仮性包茎を気にしていたりすると、性行為への自信を失い、EDを発症することがあります。その場合のEDの対策として、手術によりコンプレックスの原因を取り除くのもひとつの方法です。包茎や短小が手術によって解消されると、自信の回復につながり、EDが改善する可能性があります。
また、認識を改めることにより、コンプレックスが気にならなくなる場合もあります。2002年にオランダで行われた調査によると、大学病院で出産した女性170人のうち、77%が「ペニスの長さを重要としていない」と回答しました。
この結果を受け「ペニスのサイズや形には個人差があり、気にする必要はない」と考えれば、コンプレックスの解消につながるかもしれません。
参考:National Library of Medicine「What importance do women attribute to the size of the penis?」
普段、床や壁を使うような刺激の強い方法でオナニーをしている場合、通常の性行為では物足りなくなり、勃起しづらくなる可能性があります。EDの対策として、オナニーの方法を刺激が強すぎないものに変えることで、改善を図れるでしょう。
いきなり切り替えることは難しいと感じる方は、射精の直前で手に切り替えることからはじめ、徐々に手だけで行うようにすれば、次第に強い刺激でなくても快感を得られるようになるでしょう。
EDの対策として、ホルモン補充療法を受けるのも一つの方法です。性欲や生殖器の発育に関わる男性ホルモンのテストステロンが少ない場合、EDを発症する可能性があります。テストステロン値は、血液検査により確認することが可能です。ホルモン補充療法では、塗り薬や貼り薬、注射薬、経口内服薬などを使用します。医師に相談したうえで、症状に適した治療法を選択しましょう。
EDの原因が糖尿病や肥満、高血圧などの内科疾患の場合、疾患の治療を行うことでEDの症状も改善する可能性があります。健康診断で糖尿病の可能性や肥満・高血圧などを指摘されたものの治療を受けていない方は、医療機関で再検査を受け、疾患の治療を行いましょう。
EDの対策として、ED治療薬の服用が効果的です。ED治療薬は、勃起を収束させるPDE5という酵素の働きを抑えることで、血管を広げて陰茎への血流を増やし、勃起を促進します。
日本で認可されているED治療薬は、以下の3つです。
| ED治療薬の種類 | 特徴 |
|---|---|
| バイアグラ | ・1999年に発売された ・ジェネリック医薬品は「シルデナフィル」 ・比較的価格が安い ・食事の影響を受けやすいため、空腹時に服用する必要がある ・効果が現れるまでにかかる時間は30分~1時間 ・効果の持続時間は3~5時間 ・効果のピークは服用から1~2時間後 |
| レビトラ | ・2004年に発売された ・ジェネリック医薬品は「バルデナフィル」 ・水に溶けやすく、即効性がある ・高脂肪食を除き食事の影響は受けにくい ・効果が現れるまでの時間は15~30分程度 ・効果の持続時間は4~8時間 ・効果のピークは服用してから1〜2時間後 ・先発医薬品のレビトラは2021年10月に販売中止となり、現在はジェネリック医薬品のバルデナフィル錠が代替薬として処方されている |
| シアリス | ・2007年に発売された ・副作用が出現しにくい ・食事の影響を受けにくく、好きなタイミングで服用できる ・効果が現れるまでにかかる時間は30〜60分程度 ・効果の持続時間は30~36時間 ・金曜日の夜に服用すると日曜の昼頃まで効果が持続するため、「ウィークエンドピル」とも呼ばれる ・効果のピークは服用してから3時間後 |
ED治療薬はドラッグストアでは販売されておらず、服用するには医師の処方が必要です。服用中の薬や既往歴がある際は受診時に医師に伝え、飲み合わせやED治療薬の服用が問題ないか判断してもらいましょう。
ED治療薬を服用した際は副作用が出る場合があり、主な症状は以下のとおりです。
ただし、ほとんどは軽度で一過性のものとされています。
なお、頻度は少ないものの、注意すべき副作用として以下が挙げられます。
非動脈炎性前部虚血性視神経症や突発性難聴は、国内での症例は報告されていません。持続勃起症は、国内で1名報告があるとされていますが、世界的にも極めてまれな副作用です。万が一、ED治療薬の服用後、4時間以上勃起が続く場合は早急に受診しましょう。
EDの治療を受けるには、泌尿器科やED専門のクリニックに足を運ぶ方法のほか、オンラインクリニックを受診する方法があります。ここでは、それぞれの受診方法について解説します。
対面で受診したい場合、泌尿器科やED専門のクリニックに行きましょう。受診した際は、症状の確認とともに、病歴や生活習慣などに関する問診を受けます。必要に応じて、血圧測定や血液検査などを実施する場合があるでしょう。
対面診療は、医師と直接対面して相談したり、必要に応じて検査を受けられたりするのがメリットです。一方、通院時間や交通費などがかかることがデメリットとして挙げられます。
通院の手間を省きたい人や受診することを周囲に知られたくない人は、オンラインクリニックがおすすめです。オンラインクリニックとは、スマートフォンやパソコンを使ってビデオ通話などで診察を受けられる医療機関です。
医師の診察を受け、ED治療薬が処方された際は、配送で受け取れます。クリニックに足を運ばずに自宅で診察を受けられるほか、以下のメリットがあります。
ただし、オンラインクリニックは問診票に沿って自覚症状を確認することがメインであり、検査は受けられません。内科疾患の可能性がある場合、内科の受診が必要になるケースもある点を考慮しましょう。
EDとは、性行為時に「十分に勃起しない」「勃起しても持続しない」といった状態を指します。EDになる原因には、心因的要因や器質的要因のほか、薬剤の副作用、混合的要因が考えられます。
EDになった場合の対策や対処法として挙げられるのは、以下のとおりです。
EDの対策を行う場合、EDの原因に応じて内科疾患の治療や生活習慣の改善などを行うとともに、ED治療薬を服用するのがおすすめです。ED治療薬は、血管拡張作用により勃起をサポートします。
レバクリでは、ED治療薬のオンライン処方を行っています。場所や時間にとらわれずにビデオチャットや電話で診察が受けられ、処方された薬は自宅など好きな場所に届きます。診察料は無料なので、ぜひご予約ください。