更新日:2024年01月11日
はげは、ある程度年齢を重ねてから起こるものと考える方も多いでしょう。しかし、10〜20代の方でも、はげる可能性はあります。
本記事では、若い年代の方がはげてしまう「若はげ」がなぜ起こるのか解説します。また、若はげの見分け方や対策についても紹介するので、若はげについて悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
若はげは、正式には「若年性脱毛症」と呼ばれており、若年性脱毛症の多くはAGAが原因とされています。日本皮膚科学会が発表している男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版によると、AGAは思春期以降に始まるとしており、年令別AGA罹患者の割合は20代で約10%、30代で20%となっています。つまり、20代では10人に1人、30代では5人に1人がAGAによる若はげを発症しているのです。
ここでは、なぜ若はげが発生するのか、原因を解説します。
参考:公益社団法人 日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版」
AGAによる若はげの原因は、男性ホルモンであると考えられています。男性ホルモンの1種であるジヒドロテストステロンが、毛包にある男性ホルモンレセプターと結合することで、脱毛因子を生成し、抜け毛が増えていきます。これが若はげが起こるメカニズムです。
ジヒドロテストステロンは、男性ホルモンの1種であるテストテロンが5αリダクターゼという酵素によって変換されることで生成されます。
テストステロンがジヒドロテストステロンに変換されやすいかどうかは、遺伝が関係しています。変換酵素である5αリダクターゼの分泌量や男性ホルモンの受容体の数が遺伝の影響を受けると考えられているのです。
生活習慣もAGAによる若はげを進行させる原因の1つになると考えられています。特に、食事や睡眠の質が悪いと、若はげにつながってしまうでしょう。
髪に必要な栄養素は、髪の主成分であるタンパク質や、髪の生成を助ける亜鉛やビタミンなどです。食生活が偏りこれらの栄養素が摂取できていないと、若はげが進行する可能性があります。また、脂っこい食べ物や塩分は、血液をドロドロにしたり頭皮のべたつきの原因になったりするため、頭皮環境の悪化につながり、髪の成長を阻害します。
カフェインやアルコールといった嗜好品にも注意が必要です。カフェインは毛髪を成長させる毛乳頭に直接作用して、発毛促進因子であるFGF-7の産生量を高めるアデノシンの働きを阻害します。アルコールも肝臓で分解されたときにできるアセトアルデヒドという産物が、ジヒドロテストステロンを増加させるともいわれています。
髪に必要な栄養素が摂取できておらず、かつ脂質やカフェイン、アルコールを偏って摂取している場合は、若はげの原因となっている可能性があります。
睡眠時間が短かったり質の悪い睡眠をとっていたりすると、髪の成長に関わる成長ホルモンが十分に分泌されません。睡眠時間はもちろん、睡眠の質が担保されていなければ薄毛になるリスクが高まります。
誤ったヘアケアが、AGAを進行させ若はげの原因になることもあります。洗浄力の強いシャンプーを使っていると、頭皮に必要な皮脂まで洗い流してしまい、頭皮環境が悪化します。頭皮環境が悪化すると、フケやかゆみ、毛穴のつまりなどを引き起こし、若はげになる可能性を高めてしまうのです。
また、整髪剤をつかってスタイリングをした後にしっかりと洗い流さずに就寝してしまうと、毛穴を詰まらせて若はげのリスクを高めます。特に、ヘアワックスやジェルには合成界面活性剤といった成分が含まれており、この合成界面活性剤は、髪の毛の主成分でもあるタンパク質にダメージを与えて破壊してしまうことから、抜け毛のリスクをより高めてしまうと考えられています。
ストレスはAGAの直接の原因にはならないとされていますが、抜け毛の原因となり、間接的にAGAの進行を助長させることがあります。
ストレスがたまると交感神経の働きが活発となり、自律神経の乱れにつながります。自律神経が乱れてしまうと、リラックス時や休息時に優位となる副交感神経の働きが抑えられてしまい、結果として睡眠の質が低下したり、血行不良になったりします。
血行不良となれば毛根に十分な栄養を送ることが難しくなります。また、睡眠の質が低下すれば、成長ホルモンが十分に分泌されず髪の成長を阻害します。その結果、抜け毛が増えてしまい、若はげとなる可能性があるのです。
大きなストレスを一気に受けたり、小さいストレスが溜まって大きくなっていくことで、若はげになる可能性がより一層高まります。
喫煙や飲酒は若はげの原因になると考えられています。タバコに含まれるニコチンには毛細血管を収縮させる作用があります。血管が収縮することで髪に十分な栄養が行き渡らなくなり、結果として若はげにつながってしまうのです。
また、若はげの原因になるとされているDHT(ジヒドロテストステロン)の濃度は、非喫煙者に比べて喫煙者の方が14%高くなることも報告されており、AGAを進行させる要因になる可能性があります。
飲酒と薄毛の関係については、「飲酒すると薄毛になる?アルコールが髪に与える影響を解説」を参照してください。
参考:National Library of Medicine「The relation of smoking, age, relative weight, and dietary intake to serum adrenal steroids, sex hormones, and sex hormone-binding globulin in middle-aged men」
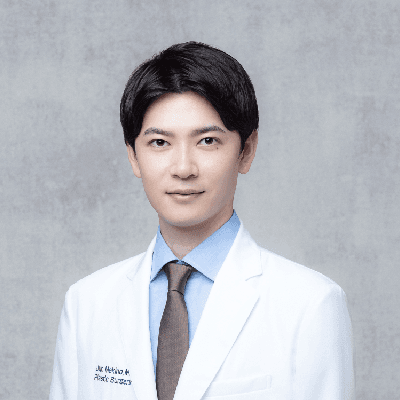
この記事の監修:
慶應義塾大学医学部卒業。日本形成外科学会認定専門医。 医師免許取得後、外資系経営コンサルティング企業のヘルスケア・IT領域にて従事。 慶應義塾大学医学部助教を経て、美容医療を主としたJSKINクリニック、及びオンライン診療サービス「レバクリ」監修。
<所属学会> 日本形成外科学会 日本美容外科学会(JSAPS)
髪を常に引っ張るようなヘアスタイルが、若はげの原因になっている可能性もあります。髪を常に引っ張るヘアスタイルは、引っ張られている状態が長時間続くことで毛包が傷ついてしまう牽引性脱毛という脱毛症を引き起こします。
今の自分の状態が若はげなのか一時的なものなのかが分からないという方もいるかもしれません。ここでは、今の自分の状態が一時的なものなのか、若はげなのかを見分ける方法を解説します。
今までと比べて抜け毛が明らかに増えたという場合には、AGAによる若はげである可能性が考えられます。
一般的に髪の毛は1日50~100本抜けるといわれています。夏から秋にかけては特に抜け毛が増えやすい時期で、1日200本程度抜けると考えられており、この本数であれば問題はありません。しかし、これ以上の本数が抜ける場合には、若はげの可能性があります。起床時、枕にある抜け毛が明らかに増えている場合や、シャンプー時に抜け毛が多く見られる場合は要注意です。
また、抜けた毛の状態でも若はげかどうかを見分けるポイントがあります。抜け毛の根元に黒い毛根が付着していたり、毛根の形が細長かったりしている場合には、若はげによって髪が十分に成長できずに抜けている可能性があります。
AGAの場合、生え際から抜け毛が進行していくことが多くみられます。そのため、おでこが広くなったように感じたり、以前より生え際のM字が目立つと感じたりした場合には、若はげの可能性が高いといえます。
また、AGAは頭頂部の髪の毛が薄くなっていくタイプもあります。生え際については問題なくても、頭頂部が薄いと感じる、あるいは生え際と頭頂部の両方が薄くなっていると感じた場合には若はげである可能性が高いです。
頭頂部の状態を確認する場合は、写真を撮ったり、鏡を2枚用意して後ろと前から確認したりすると良いでしょう。つむじが見えやすくなっていたり、地肌が見えたりしている場合は、AGAによる若はげが疑われます。
若はげの進行を抑えるためには、次の対策をしてみてください。
若はげの対策としてまず挙げられるのが生活習慣の見直しです。特に、若はげの原因となる睡眠不足や乱れた食生活を改善させていきましょう。
髪の成長に重要なタンパク質、亜鉛、ビタミンを食事で摂取すると、若はげの対策になるでしょう。タンパク質は髪の毛の主成分で、約80~85%がタンパク質で構成されています。このタンパク質を生成するサポートを行うのが亜鉛とビタミンです。
また、脂っこい食べ物や塩分は血液をドロドロにしたり、頭皮のべたつきの原因になったりするため、頭皮の環境を悪くして、髪の成長を阻害します。これらの食べ物を過剰に摂らないように注意しましょう。抜け毛につながるアルコールやコーヒーの過剰摂取も控えると良いでしょう。
若はげを対策するには、十分な睡眠時間を確保し、かつ質の高い睡眠をとることが重要です。
髪の毛の成長には、成長ホルモンが関係しますが、この成長ホルモンは午後22時~午前2時に多く分泌されるといわれています。成長ホルモンが分泌されるタイミングで質の高い睡眠がとれるように、睡眠の3時間前までには食事を終わらせて、睡眠前に消化が終わるようにしましょう。満腹で眠ってしまうと、就寝後にも消化が続き、眠りが浅くなってしまいます。
また、脳の覚醒の原因になるとされるメラトニンの分泌を抑制しないよう、寝る前にはブルーライトの光を見ないようにして、質の高い睡眠を確保しましょう。
ストレスも抜け毛や薄毛の原因になると考えられているため、できる限りストレスをためないようにしましょう。少しのストレスでも、蓄積され続けると大きなストレスとなり、抜け毛や薄毛に影響します。運動や入浴など、自分にぴったりなストレス解消法を見つけて実践していきましょう。
シャンプーやヘアケア方法を見直すことも若はげの予防につながります。自分に合わないシャンプーを長期間使用していれば頭皮環境を悪化させかねません。また、洗浄力の強いシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで洗い落としてしまうため、かえって頭皮環境を悪化させてしまいます。シャンプーを変える場合は、頭皮にやさしいアミノ酸系シャンプーがおすすめです。
また、ワックスなどの整髪剤を使用した場合、その日のうちに整髪剤をシャンプーで落とすことを心がけると良いでしょう。ワックスなどの整髪剤がなかなか落ちず、ついシャンプーを数回行ってしまうかもしれませんが、シャンプーを複数回行うことも、頭皮の環境を悪くするリスクがあります。ワックスなどの整髪剤を使用したときには、まずお湯で十分に予洗いをして汚れを落としてからシャンプーを使って髪を洗うと良いでしょう。
若はげを本気で何とかしたいという方は禁煙や節煙にも挑戦してみましょう。禁煙をすれば、若はげの対策にもつながるといえるでしょう。
どうしても禁煙が難しい場合は、まずは徐々にタバコの本数を減らしてみたり、禁煙外来を活用したりするのも良いでしょう。
若はげはAGAクリニックなどの医療機関で治療ができます。AGAは基本的に治療薬を使って治療していきます。AGAクリニックで処方してもらえる治療薬は次のとおりです。
フィナステリドは内服するタイプの薬です。フィナステリドは、5αリダクターゼII型の活性を阻害し、テストステロンをジヒドロテストステロンに変換させないようにして抜け毛を抑制する効果が期待できます。
5αリダクターゼにはI型とII型があり、I型は側頭部や後頭部に、II型は前頭部や頭頂部に多く分布しています。ジヒドロテストロンへ変化しやすいのは5αリダクターゼII型とされているため、フィナステリドを服用することで、薄毛や抜け毛の改善効果が期待できるのです。
日本皮膚科学会の「AGAガイドライン」によると、臨床実験において48週間の継続服用で50%以上の軽度改善効果が見られており、フィナステリドは推奨すべき治療法としています。また、1日あたり1mgのフィナステリドを5年間継続内服した結果、99.4%の方に効果が得られたとも報告しています。40歳未満ではさらに高い効果が得られており、若はげへの高い効果も期待できるでしょう。
副作用として肝機能障害、勃起不全、リビドー(性欲)減退、精液量減少、射精障害などがあります。
フィナステリドについて詳しく知りたい方は、「フィナステリドの効果とは?副作用や服用時の注意点についても説明」も参考にしてみてください。
参考:公益社団法人 日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版」
デュタステリドも、フィナステリドと同様にAGAの進行を抑制する効果がある内服薬です。フィナステリドと異なる点は、デュタステリドは5αリダクターゼのI型、II型の両方を阻害できる点です。そのため、AGAの原因が5αリダクターゼI型によるものである場合にも高い効果が期待できるでしょう。
デュタステリドの副作用としては、リビドー減少、インポテンツ、射精障害などがフィナステリドより高い確率で起こるとされています。また、デュタステリドは、20歳未満の方の服用は推奨されていません。
ミノキシジルは、患部に塗布するタイプの外用薬です。頭皮に塗布することで毛包に直接作用し、細胞の増殖やタンパク質の合成を促進して発毛を促します。副作用としてかゆみや紅斑、フケ、毛包炎、接触皮膚炎、顔面の多毛などが出現する可能性があります。
ミノキシジルについては、「ミノキシジルの効果とは?副作用や他のAGA治療薬との違いも解説」でも詳しく解説しています。
若はげの治療をするうえで注意しておくべきことがいくつかあります。ここからは若はげの治療で注意すべきことを解説します。
若はげの治療をした際には薬を自己判断で中断しないように注意しましょう。AGAガイドラインにおいても、AGA治療薬を使用した治療は6ヶ月は継続するようにとしています。そのため、効果が見られなくても自己中断はせずにまずは使用を続けましょう。治療中に何か気になることがあれば、まずは医師に相談することをおすすめします。
参考:公益社団法人 日本皮膚科学会「男性型および女性型脱毛症診療ガイドライン 2017 年版」
もしも、上述した薬の紹介に挙げられている副作用と思わしき症状が出現した場合にはすぐに医師へ相談しましょう。副作用を放置して使用し続けると頭皮環境や体調が悪化する可能性もあるため、早めの相談が重要です。
若はげは若年性脱毛症といい、AGAが原因となっている可能性が高い疾患です。AGAは男性ホルモンの影響が主な原因となりますが、ほかにも生活習慣の乱れやストレス、誤ったヘアケアなどによって、AGAによる若はげが進行することも考えられます。
また、若はげは専門のクリニックで治療することが可能です。少しでも若はげを改善したいという場合には、AGAクリニックを受診して、治療を始めてみてはいかがでしょうか。